特許申請の動向:人工知能(AI)関連発明の増加に注目
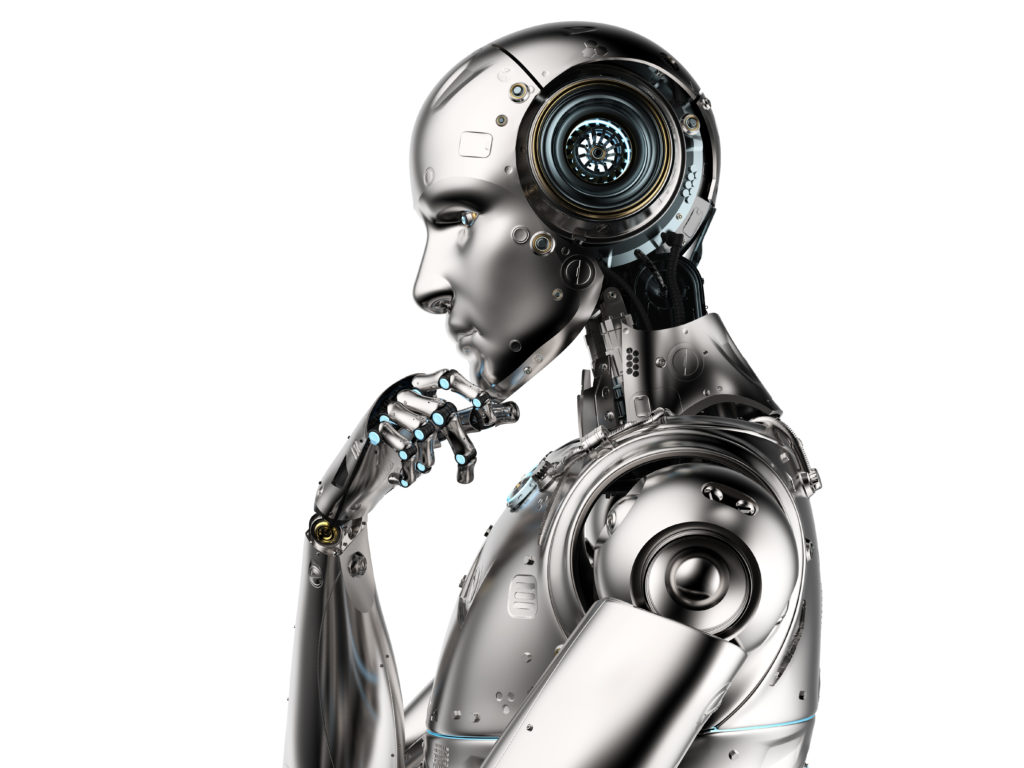
AIに関する特許出願動向の調査報告書によると、国内外での人工知能(AI)に関する特許出願件数は急増しており、特に第三次AIブームの影響により2014年以降顕著な増加が見られました。以下に、報告書で述べられている重要なポイントをまとめました。
- 国内AI関連発明の出願件数: 2018年には国内AI関連発明の出願件数が4,728件となり、前年比で約54%増加しました。この増加傾向は第三次AIブームの影響によるものであり、特に深層学習(ディープラーニング)に言及する出願件数が増加しています。2018年の国内特許出願件数の半数以上が深層学習に関連するものでした。
- 技術分野と適用分野: AI関連発明は、AIコア発明に加え、様々な技術分野に適用された発明も含まれます。報告書によれば、AIの適用分野は医学診断、制御系・調整系一般、交通制御、画像処理、ビジネス、情報一般、音声処理、マニピュレータ、材料分析、情報検索・推薦、映像処理、自然言語処理など、多岐にわたっています。特に制御・ロボティクス関連と医学診断分野でのAI関連発明の伸び率が高いです。
- 主要企業の特許出願件数: AI関連発明において、NTTが最も多くの特許出願件数を有しています。深層学習に限定すると、NTTが1位で、ファナック、富士通、キヤノンが続いています。富士通や日立製作所もAI関連特許出願において大きな存在感を示しています。
- 出願動向の国際比較: AIコア技術に関する出願は、日本、米国、欧州特許庁、中国、韓国の5つの特許庁およびPCT国際出願においても増加傾向にあります。特に中国と米国の出願件数が突出しており、中国が6,858件、米国が5,954件となっています。中国はAIに対する積極的な政策や投資を行っており、特許出願件数の増加がその成果として現れています。米国もAI技術の発展を重視しており、多くの企業や研究機関がAI関連の特許出願を行っています。
これらの調査結果から、AI関連の特許出願は急速に増加しており、特に深層学習やAIの適用分野において活発な動きが見られます。企業や国家がAI技術の保護と競争力の確保に積極的に取り組んでいることが伺えます。
特許出願を行う際には、既存の特許や技術との関連性や独自性の確保が重要です。また、国内外の特許制度や出願手続きについても理解する必要があります。特許庁や専門家の助言を受けながら、特許戦略を構築することが特許出願の成功につながるでしょう。
さらに、技術の進化や市場の変化に合わせて特許戦略を見直すことも重要です。AI技術は急速に進歩しており、新たな技術や応用分野が生まれています。特許戦略の柔軟性を持ちながら、技術の先行開発や競争力の維持・強化に取り組むことが求められます。
特許出願は技術の保護だけでなく、企業の価値向上や競争優位性の確保にもつながる重要な手段です。特許に関する情報を積極的に収集し、自社の特許戦略を構築していくことが、企業の成長と成功に貢献するでしょう。





